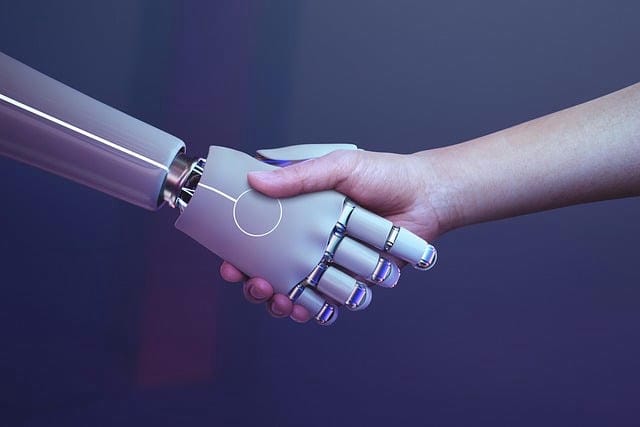
企業や組織が業務を遂行するうえで、情報端末の活用は不可欠となっている。ノートパソコンやデスクトップパソコン、スマートフォン、タブレット端末など多様な機器が業務現場で用いられているが、これらの端末はインターネットや社内ネットワークを介して組織内外とデータをやりとりしており、サイバー攻撃の標的となる危険性がある。このため、情報資産やネットワーク全体を守るために、端末自体への防御策が求められる。それがエンドポイントセキュリティである。従来、外部からの不正侵入防止策といえば、ネットワークの外縁部で実施するものが主流だった。
ネットワーク境界に防御装置を設置し、外部からの有害トラフィックやマルウェアの流入を検知して遮断するという考え方である。だが、従業員のリモートワークや社外からのモバイルアクセスが常態化することで、ネットワーク自体の境界が曖昧になってきた。また、インターネット経由でクラウドサービスを直接利用する場面も急増し、従来の防御策では不十分であるという認識が広まっている。こうした状況下では、利用する端末そのものがサイバー攻撃の最前線となるため、各端末に適切な防御機能を設けることが極めて重要となる。サイバー攻撃の手法は年々巧妙化している。
標的型メール攻撃や不正なウェブサイトへの誘導によるマルウェア感染、脆弱な端末を踏み台にした内部不正など、その種類は多岐にわたる。たとえば、正規の通信に見せかけて不正プログラムを忍び込ませるケースや、ソフトウェアのぜい弱性を突いて遠隔操作を行う手法など、一瞬の油断が被害拡大につながる。端末利用者だけでなく、組織のすべての関係者がセキュリティ意識を高めることも重要だが、それと並行して技術的対策が欠かせない。エンドポイントセキュリティの主な対策としては、ウイルス対策ソフトが古くから用いられてきた。これは、不正な動作やファイルパターンを検出して駆除する手法であり、既存の脅威に対しては一定の効果を発揮する。
しかし、未知の脅威や巧妙な攻撃方法については従来型の対策だけでは対応が困難である。このため、振る舞い検知や機械学習を活用した高度な不正検知、ゼロデイ脅威への即時対応、さらには侵入発生時の自動隔離など、多層的な防御を組み合わせて導入する傾向が強まってきている。端末にはさまざまな情報資産が蓄積されているため、盗難や紛失による情報流出も大きなリスクとなる。たとえば、機密情報や個人情報、顧客情報などが端末から持ち出された場合の損失は計り知れない。そのため、ハードディスク全体の暗号化や、通信経路の暗号化、さらには不正なデバイス接続制御といった機能もエンドポイントセキュリティの一部となる。
これにより、不正アクセスや持ち出しリスクを低減することができる。また、ソフトウェア管理も無視できないポイントである。端末にインストールされたアプリケーションやオペレーティングシステムにぜい弱性が残されていれば、不正侵入やサイバー攻撃の足掛かりとなる可能性が高まる。ソフトウェアの定期的なアップデートやパッチ適用を徹底し、不要なプログラムのインストールを制限するといった運用上の取り組みも必要不可欠である。エンドポイントセキュリティの導入には、単純なソフトウェア導入だけでなく、組織の業務フローや利用実態に即した管理体制の整備が求められる。
たとえば、大規模な組織では数百台から数万台におよぶ端末を一括で管理するため、統合的な管理ツールの活用が効果的である。これにより、各端末のセキュリティ状況をリアルタイムで把握したり、インシデント発生時の初動対応や原因の特定を迅速に実施できる。また、端末のリースや貸与、返却時にも確実なデータ消去や設定リセットといった一連のプロセスを通じて、不正利用や情報流出を防止できる。人的リソースが限られる中小組織においては、すべての対策を専門スタッフで担うことが難しい場面も少なくない。そのような場合は、自動化機能の活用や専門事業者による運用支援といった方法も選択肢になる。
いずれにせよ、端末の使用実態と最新のサイバー攻撃動向を見極め、コストパフォーマンスとリスク低減効果を総合的に評価したうえで、継続的な対策強化を図ることが重要である。最後に、エンドポイントセキュリティは一度導入して終わりではない。攻撃者は日夜新たな手口や不正方法を編み出しており、防御する側もそれに対応した柔軟かつ持続的な見直しと改善が欠かせない。情報セキュリティ部門やシステム部門のみならず、全従業員がエンドポイントの安全利用に意識を持ち、組織として一体となってサイバー攻撃や不正の脅威から情報資産を守ることが求められるのである。企業や組織の業務において、パソコンやスマートフォンなどの情報端末の活用は不可欠となり、同時にサイバー攻撃の標的となるリスクが高まっています。
従来はネットワークの境界に防御策を設ける手法が主流でしたが、リモートワークやクラウドサービスの普及により、その効果が限定的になっています。このため、各端末自体へのエンドポイントセキュリティ対策が重要視されています。サイバー攻撃は年々巧妙化し、標的型攻撃やマルウェア感染、ソフトウェアの脆弱性を突く手法など多岐にわたるため、ウイルス対策ソフトだけでなく、振る舞い検知や自動隔離、暗号化といった多層的な技術的対策が不可欠となっています。また、端末の盗難や紛失による情報流出リスクも考慮し、デバイスや通信の暗号化、不正アクセス防止策も導入する必要があります。ソフトウェアやOSの更新・パッチ適用も基本的な対策であり、不要なプログラムの排除も重要です。
大規模組織では管理ツールを活用して端末を一元管理し、中小組織では自動化や外部支援も有効な手段です。これらの対策は導入して終わりではなく、攻撃手法の進化に合わせて継続的に見直すことが求められます。全従業員がセキュリティ意識を持ち、組織全体で情報資産を守る姿勢が不可欠です。
